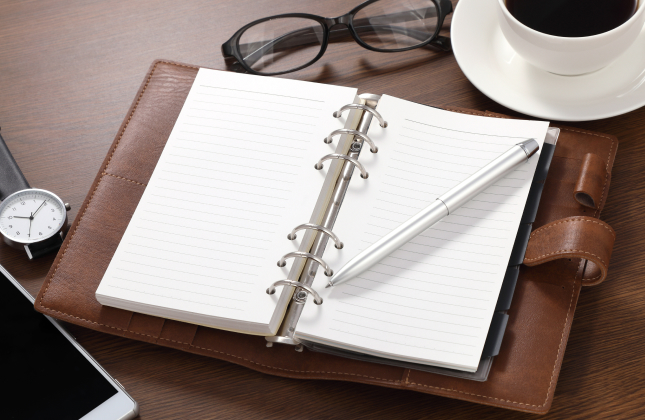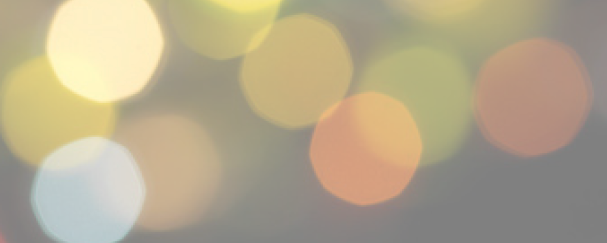TALK SESSION
働く環境座談会

日本年金機構では職員が働きやすい職場環境を確立するために働き方改革のさらなる促進に取り組んでいます。
その改革はどのように実を結んでいるのでしょうか。
実際に働いている職員の皆さんに集まっていただき率直な意見をいただきました。
MEMBERS
-

府中年金事務所
国民年金第2課長O
2001年入庁
国民年金第2課を総括。主に保険料収納対策について、どのようなアプローチが効果を発揮するかなどをマーケティング的な見地を踏まえて立案。
-

人事部 人事企画室
人事企画グループT
2012年入構
人事企画グループに所属。職員のやりがい向上や働きやすい職場環境を実現するための人事制度や給与制度を企画し、制度化する業務に従事。
-

世田谷年金事務所
厚生年金適用調査課J
2015年入構
厚生年金適用調査課に所属。事業所から提出された賃金台帳や出勤簿などを調査し、届出のもれや誤りがないか審査する業務を担当。
-

横須賀年金事務所
お客様相談室K
2020年入構
お客様相談室において主に年金請求書等の書類審査を担当。そのほかお客様からの電話応対、窓口対応、総合案内なども務めている。

#01 日本年金機構を志望した理由と入構前後のギャップは?

日本年金機構は公的年金を取り扱っている日本で唯一の組織であり、多くの人々の生活を支える仕事に魅力を感じて志望しました。さらに全国に年金事務所があることから、自分のライフスタイルや生活拠点が変化したとしても安心して長く働ける環境があることも理由の一つです。

私もKさんと似ていますが、「人のためになる仕事がしたい」と社会貢献度の高い年金制度に携わりたいと志望しました。もともと文学部史学科で考古学を学んでいまして、発掘資料の見方や遺物の研究をしていたこともあって公的な仕事に興味を持ったのもきっかけです。

私は、一つ目に就職活動の時期と日本年金機構の発足がほぼ同時期だったことからこの組織に興味を持ち、新たに生まれ変わった組織の一員として、ともに成長しながら貢献していきたいと思ったこと。二つ目に会社の利益のために働くよりも国民の生活を支えるために欠かせない社会経済インフラの役割を担う業務に魅力を感じたこと。最後に全国異動がある組織に入って、さまざまな場所で働いて色々な経験を積んでみたいと考えたためです。

私は社会保険庁時代の採用ですが、学生時代から国や地域のために働くことが仕事をしていく上での動機付けになると考えていたことから、公務員を目指しました。中でも少子高齢化の進む日本において、社会保障の果たす役割が大きくなると考えたのが入庁のきっかけでした。振り返ると、採用面接時に「うちは大変だけどやりがいがあるよ」と面接官の方がおっしゃっていたのを思い出します。入庁後しばらくして霞が関の本庁に異動となりましたが、当時は業務量も多く大変な日々でしたので、入庁する前と後で特に大きなギャップは感じませんでした。

私は、入構前に年金事務所を訪れて職場見学をしたのですが、その時は、「個人ごとに与えられた業務を淡々とこなす感じなのかな」と漠然と思って見ていました。ただ、入構してみると、チームで業務を進めることが多く、業務で悩みごとがある時は担当する職員全員で課題を共有して目標達成に向けて取り組むなど、チームとしての一体感をとても大事にしていたので、最初に見て思っていたイメージとのギャップがありました。

私は、「年金」というと老齢給付のイメージが強かったのでお客様は高齢者の方々ばかりと思っていましたが、実際は学生の方など幅広い年齢層のお客様が来所されることに驚いたのを覚えています。

私が感じたギャップは若手職員の意見を積極的に取り入れてくれるところです。「この仕事はやめられるのでは」キャンペーンもその一つで、若手やベテラン関係なく誰でも意見を述べられる環境にギャップを感じました。

このキャンペーンは良かったですよね。年金事務所で行う実務のうち、不効率となっている業務について、実務を担う現場からの声を聞ける機会となりましたし、提案のあった意見を本部の担当部署で検討した結果、実際に業務が見直された事例も多いですから。

Kさんは「この仕事はやめられるのでは」キャンペーンに意見は出しましたか?

私は出さなかったのですが、皆さんの意見を拝見して「確かにそうだな」と感じています。

基幹システムを抜本的に変更するような対応はすぐには難しいですが、業務方法の見直しなどは現場からの意見を早急に検討、実施していて、業務改善につながる良い取組だと思います。

実際に、ここ数年で年金事務所の業務が変わってきているなと私も感じています。

私もそう思います。

若手職員のお二人から変わってきていると感じてもらえるのはうれしいですね。実は、私とTさんは、かつて本部で一緒に働いていたことがあるのですが、その時に携わったのは、再生プロジェクトの一環として現場の声を吸い上げながら組織改革、業務改革、人事改革などを進めていく業務でした。「この仕事はやめられるのでは」キャンペーンはその流れから続いているものだと思っています。
#02 人事異動や人事制度についてどう感じている?

私は地元が福島県で大学は東京でしたが、就職活動をしていた時は東京と福島のどちらで就職するか決めきれていませんでした。日本年金機構は全国に拠点がありますし、一度働く都道府県を決めたとしても自分の意向を伝える機会があるので、臨機応変に対応してもらえるということで全国転勤をプラスに考えるようになりました。

KさんとJさんはこれまでに異動の経験はありますか?

最初は地元の福島県に配属になり、宮城県仙台市の事務センターを経て、現在は神奈川県横須賀市の年金事務所に所属しています。引越しは大変ですが、転勤するたびに新しい出会いがありますし、さまざまな人から良い部分を吸収できていると感じています。

私は出身が東京ですが、入構後の配属先は大阪の年金事務所でした。これまで生活したことのない地域でしたのでびっくりましたが、職員の方々は皆さん温かい人ばかりで休日は一緒に遊びに行くなど楽しかったのを覚えています。希望して二年後に東京勤務となりましたが、大阪を離れるのが寂しかったくらいです。



Jさんは大変だったと思いますが、最近はKさんのように最初の配属地から希望する地域になるべく配属となるように配慮されていますよね。私は長崎県出身ですが、最初の配属先は広島県の福山年金事務所でした。縁もゆかりもない場所だったので意外でしたが、新幹線が通る駅だったので地元にも帰りやすかったですし、福山市は中国地方の各県をはじめ、四国、関西地方にもアクセスがよく、週末や休日にはさまざまな観光名所を巡ることができて楽しかったです。その時の職場の先輩には、異動して10年以上経った今でも連絡を取り合う方もいて、本当に充実した2年半でした。

Kさんは現在横須賀年金事務所ということですが、異動希望を出したんですか?

はい、人事部に神奈川県に異動したい事情を伝えた結果、横須賀年金事務所に配属となりました。

全国転勤だと心細いこともあったかもしれませんが、最近は毎年多くの新規採用者が入構してくれているので、異動先にも採用同期や年齢が近い先輩や後輩などが周りに多いと思います。その点では安心できますよね。

はい。それと全国転勤でいうと、横須賀の前は仙台に住んでいたのですが、私はずっと福島に住んでいて、一度は仙台に住んでみたいなと思っていたんです。全国転勤の機会がなければ絶対に住んでいませんでしたし、異動することで気持ちの切替えもできるので、学生の皆さんには「全国転勤の機会があるのはチャンスでもあるよ」とお伝えしたいです。

確かにそうですね。私は子どもがまだ小さいので全国転勤は難しいですが、そういった人には家族事情を配慮した異動をしてもらえるのもうれしいです。

他にも採用後6か月の間に年金事務所の主要業務をジョブローテーションで学ぶことができるのもありがたかったです。

新入構員の時に年金事務所の主要4業務を経験できる貴重な機会ですし、配属された年金事務所の職員の名前やそれぞれの担当業務を覚えることができるのもいいですよね。

そうですね。実際に、お客様からさまざまな届出があった際に名前と担当業務を覚えていたことでスムーズに担当の課室につなぐことができました。また、部署を異動しても業務内容がわかるのも安心できます。

そういった意味ではジョブローテーションは非常に有意義な制度だと思います。配属先以外の業務を一通り経験していることは、経験していない場合と比べて実際の現場での対応力に大きな差が出ることは間違いないと思います。

入構してすぐにさまざまな業務を経験することで、自分の適性を知ることができるのも良いですよね。経験を重ねる中で、ゆくゆくは自分の適性にあった部署で組織の中核を担っていただくことが一番良いと思いますので、早い段階で日本年金機構がどんなことをやっているのかを経験することは大事だと思います。
#03 年金事務所と本部の役割は?

私はこれまで3か所にわたって年金事務所での勤務が続いているので、今後は本部業務にもチャレンジしてみたいと考えているのですが…

JさんやKさんのようにライフイベントに合わせて自分の生活拠点やキャリアに対する考えも変化しますよね。人事部では、その時々の望むキャリアに合わせた異動を実現するためにご本人との面談の場を設けるなどして、将来に向けた意向確認を行っています。

人事部は各職員の希望と業務をマッチングさせることで組織のパフォーマンスを全体的に上げていこうと尽力していると思います。この一環として、本部と年金事務所間の人事異動も積極的に進めていると思います。
年金事務所は基本的にお客様への対応業務を行っている一方で、本部は企画業務や国・関係団体との調整などが業務の中心となりますので、同じ組織ではあるものの業務の性質が大きく異なります。年金事務所と本部の業務を両方経験することで、年金事務所では本部からの指示の背景を考えることができたり、本部では現場で実際にどのような状況になっているかを認識しやすくなり、結果として機構全体の力が底上げされていくと考えています。

その他にも本部では制度の企画・立案、資料作成、企画案件の関係部署全体の進捗管理を行います。このような業務は年金事務所ではなかなか経験できないので、本部での経験は必ず自分のキャリアにとってプラスになるはずですよ。

Tさんも言うように、若いうちに本部業務に携わるのはプラスになると思います。また、年金事務所の状況を把握していないと本部の企画業務などを行うことは難しいはずです。そういった意味では機構は組織としての熟成がかなり進んできていると思います。人事異動サイクルで人材育成を図り、年金事務所と本部がそれぞれ強化される相乗効果で良い組織を目指していますよね。


#04 日本年金機構の働く環境はどう変わった?

私はまだ入構5年目ですが、働く環境は本当に良くなってきていると感じています。新人時代は月20〜30時間残業していましたが現在は月に6時間ほどで、プライベートな時間が増えて働く活力も増しています。

それと、2025年4月から勤務時間も減少しますよね?

本部は9:00〜18:00が9:00〜17:45に、年金事務所は8:15〜17:15だったのが8:30〜17:15になりますね。

時間外勤務の縮減は事業目標にもなっており、大きな成果を出しています。4月からの勤務時間の短縮も含めて、働き方改革、そして女性活躍の促進についても機構は本気で取り組んでいると思います。

今、子どもが小さいので、シフト勤務を利用していまして、通常よりも30分早く出勤してその分30分早く退勤しています。保育園の迎えは私が担当していますし、家に帰ってからもやることが多いため勤務時間が15分短くなるのはとてもうれしいです。



私自身、特に変わったと感じているのは男性職員の育児休暇取得です。私が入構した当時は男性職員で育休を取得したという話を聞くことはほとんどありませんでしたが、数年前から日本年金機構では男性職員にも育児休暇等の制度取得を積極的に奨励するようになり、周りの男性職員も以前に比べ、多くの方が育児休暇を取得するようになりました。私も3年前に自分の子どもが生まれた時は抵抗感なく取得しました。

それと時間休を取得できる制度がありがたいです。例えば病院に行く必要があるとき、時間休を利用して午前中や夕方に1〜2時間休むことができるので助かっています。

私も時間休は利用していますよ。日本年金機構ではこの制度がずっとあるので割と当たり前だと思っていましたが、ほかの企業に勤めている友人から「時間休なんてあるんだ」と聞いて、まだ世の中的には当たり前ではないということに気付きました。

時間休については以前から取得できていたので、当たり前でないことに気付きにくいのかもしれませんね。それから、休暇制度の中では、子の看護休暇制度はすごく助かっています。小学生以下の子どもに対象が広がり、これまでより手厚くなりました。

私も看護休暇制度は本当に助かっています!

実は、私も育児には積極的に関わりたかったので、人事部に相談した結果、2年間ほど地元の年金事務所に異動となりました。本部勤務では通勤に片道1時間かかるので、家に着くのが20時を過ぎると子どもは寝てしまっているのですが、年金事務所の時は18時には帰宅して家族みんなで食事した後、子どもをお風呂に入れることができていました。このような配慮があることも本当に良いですよね。Jさんは育児短時間勤務の制度は使わないんですか?

当初は利用していたのですが、同じ課の女性職員がお子さんを育てながらフルで勤務されていたこともあって、私も頑張ろうと思って育児短時間勤務ではなくシフト勤務を利用することにしました。

働き方について、周囲に参考になる方がいるのは大きいですよね。

はい。といっても、仕事から帰ると子どもの前でも「疲れた〜」とか言ってしまいますが、退社したら仕事のことは忘れて気持ちを切り替えるようにしています。

私も本部で勤務していた時はシフト勤務を利用して始業時間を繰り下げ、子どもを保育園に送ってから出勤していました。そういう点でも機構は柔軟に働ける職場であることは間違いないと思います。

#05 入構を検討している方へのメッセージ

私たちの仕事は年金を受け取っている人だけではなく、事業所の方の対応をしたり、保険料を徴収したりと多岐にわたります。どの仕事も人々の暮らしを支えることにつながっているため、やりがいがあります。周りにはサポートしてくださる先輩職員がたくさんいますので、ぜひ一緒に働けたらと思います。

公的年金制度に携わる業務ですが、お客様も業務内容も配属先、職種によって大きく変わります。どの業務であってもやりがいを感じながら働くことができますので、今までの経験で得た価値観を大切に、ご自身に合う職場を見つけられることを願っています。

日本年金機構は公的年金制度の運営を担う唯一の組織であるからこそ、国民の方々の意見や時代の変化に合わせて常にサービスをアップデートしていくことが求められます。環境の変化に対応してくことは決して簡単なことではないですが、私たちの不断の努力が国民の方々の年金制度への信頼や利便性の向上につながると考えると、とても魅力のある仕事だと思います。ぜひ、皆さんの入構をお待ちしています。

公的年金制度の事業運営は日本年金機構だけが行っています。ライバルとなる組織、企業が存在しないことは大きな魅力だと思います。一方で、そのことに伴う責任も重大ですが、業務を行うこと自体が社会貢献に直結しうるということは、日々仕事をしていく上で、長期にわたって高いモチベーションを維持することにつながると感じています。興味のある方はぜひ入構を検討いただければと思います。
また、管理職の立場から言うと、業務に対して真摯に向き合うことのできる人、自分の果たすべき役割を把握しながらしっかり取り組める人と一緒に働けたらいいなと感じています。そのような方と一緒に仕事ができる日を楽しみにしています。