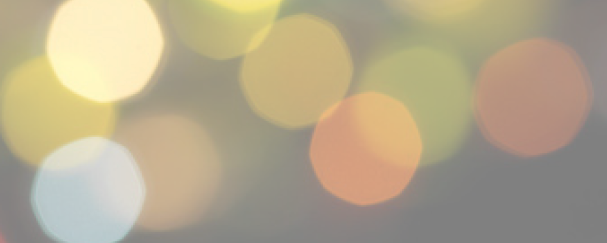年金機構について
Q.何をしている組織なの?
日本年金機構は、社会保障制度の根幹である公的年金制度(国民年金、厚生年金保険など)の業務運営を担っている唯一の組織です。
機構の前身は「社会保険庁」という厚生労働省の外局でしたが、一連の改革によって2009年12月31日で廃止され、その後の公的年金の業務運営を担う組織として、2010年1月1日に「日本年金機構」が設立されました。
Q.年金の積立金の運用もしているの?
年金積立金の運用は別の組織(年金積立金管理運用独立行政法人)が行っており、機構では行っていません。機構は、国が定めた法律に基づいて、公的年金の加入案内や保険料徴収、受給者へのお支払いなどを行っています。
業務内容について
Q.機構ならでは!の仕事ってあるの?
例えば、保険料が未納となっているお客様に対して、財産の差押えを行ったり、事業所に立ち入って調査を行うなどの業務があります。国から公権力を与えられており、他の企業、組織ではできない、非常に正義感を求められる業務も行っています。
詳しくはこちら
Q.どんなやりがいがあるの?
「お客様の生活に直接関わることができること」と答える職員が多いです。
お客様と顔を合わせて、もしくは電話で話す時間はわずかかもしれませんが、説明する内容やお預かりする書類の向こう側にはお客様の生活があるということを、常に意識することが重要です。
Q.1日の勤務時間は?
7時間45分(年金事務所は8時30分から17時15分、本部は9時~17時45分)です。
Q.デスクワークが多いの?
もちろんデスクワークの仕事もありますが、それ以外の仕事も多いです。
年金事務所では、対面でお客様の相談にお応えしたり、電話対応をする業務等があります。
一方で、高校や大学で公的年金制度の周知活動(年金セミナー)を行ったり、会社を訪問して適正な届出が行われているかを調査したりと、外出する業務もあります。
Q.車を運転することはあるの?
会社訪問や出張で、年金事務所の車(公用車)を運転することもあります。特に地方では、公用車を運転する機会が多いです。
Q.入構にあたって必須となる資格はある?
研修体制が整備されていますので、入構にあたって必須となる資格はありません。一方、私たちの仕事と関連性が高いものとしては、社会保険労務士等の資格があります。入構後に機構が定める資格を取得した場合、その取得に要した費用の一部を補助する制度もあり、自己研鑽する職員をサポートしています!
働き方について
Q.最初の配属先はどこ?
現場で実務経験を積むため、最初は年金事務所で勤務をしてもらいます。採用前に希望勤務地を確認し、原則、希望する都道府県内の年金事務所が最初の配属先になります。
まずは「業務経験を通じた能力開発期間」と位置づけ、新入構員現場研修や最初の配属先での実務等を通じて、早期の成長を促します。
Q.全国異動(転勤)はある?
職員は生活の基盤を置く都道府県(本拠地)を設定し、異動は本人の意向や適性を踏まえて本拠地にある年金事務所を中心に行いますが、組織として必要な場合は本拠地以外へ異動となる場合もあります。ただし、子育てや介護等の個別事情がある場合は転居を伴う異動について配慮されます。
働く環境について
Q.職場はどんな雰囲気?
福利厚生が充実しているだけでなく、フォローしあう体制が浸透しているため、休暇も取りやすい雰囲気です。また、業務の進め方や改善方法などに関し、職員自ら積極的にアイデアを出し、実践していくことを組織全体として推進しています。その際に年齢は関係ありませんので、若い方でもどんどん声をあげ、主体的に業務に関わって活躍することができます。
Q.職員の平均年齢は?
平均年齢は44.0歳(正規職員)です。多くの年金事務所に新卒採用の職員も配属となっていますので、年齢の近い先輩職員もいます。
Q.職員の男女比は?
正規職員は、おおむね男性6割、女性4割です。以前と比べて女性職員の割合が増えてきています。男女ともに仕事とプライベートの両立が可能となる環境整備の充実を図り、働き方改革や、女性活躍推進にも力を入れていることが理由の一つではないかと考えています。
Q.仕事と育児の両立は?
こどもが3歳までは育児休業、小学校を卒業するまでは育児短時間勤務を利用することができます。また、育児で職場を離れた職員向けに、復帰時のサポートとして学びなおしプログラムやキャリア面談を実施しています。機構の働き方改革・女性活躍の推進への取組をこちらに記載しておりますので、ご覧ください!
Q.離職率は?
入構後3年以内に離職した職員は、17.5%です。
(直近では、2021年度に入構した職員382名のうち、2024年3月末までに退職した職員が67名)
Q.制服はあるの?
制服はありません。ビジネスの場にふさわしい格好で仕事をしています。
男性はスーツ、女性はオフィスカジュアルが多いです。
キャリア・人材育成について
Q.研修制度はあるの?
機構職員として職責に求められる役割を果たすため、昇格等の節目に応じて実施する階層別研修と、職級や経験に応じた業務知識の習得を図り、制度と実務の双方に精通した人材を育成するための業務別研修が行われています。また、各年金事務所でも、情報セキュリティなどのルールの徹底を目的として、職場内研修が定期的に実施されています。研修体系についてはこちらもご参照ください。
Q.新入構員研修とは?
ビジネスマナーなどの社会人としての基礎、公的年金制度の基礎的な知識等、幅広く学んでいただきます。全国の同期採用の仲間と時間を共にしながら研修を受けるので、同期同士の結束も自然と強まります。研修を通じて得られた仲間との絆は、今後の社会人生活を送る上での大きな財産になります!
採用・選考について ※2026年度新卒採用時の内容です。
Q.選考方法は?
- ES提出
- 適性検査
- 面接(2回)
面接日時は受験者が複数の選択肢から都合の良い日時を選んでいただけますので、ご自身のスケジュールにあわせて選考を進めることができます。
Q.募集人数と過去の採用人数は?
募集人数は400名程度です。なお、2025年度に採用された新入構員は475名でした。全体の職員数が予め決まっているので、毎年度の定年退職者数等を考慮して募集人数を定めています。
Q.面接はどこで実施されるの?
一次面接はWEB面接で行いますので、ご自宅から受験していただきます。
最終面接は全国9会場で行う予定です。
Q.総合職しかないの?
正規職員は「一般職」「総合職」といった区分けはなく、全員が「総合職」です。
Q.既卒の人も応募できるの?
既卒3年以内の方まで、ご応募可能です。
Q.理系でも活躍できるの?
もちろんです!機構の業務を支えるシステムは、日本でも有数の大規模システムです。
これらの安定的な稼働を支え、年金制度改正によるシステムの改修、開発などを行う部署では、理系出身の職員も多く活躍しています。
Q.日本年金機構の正しい呼び名は?
「御機構」と呼ぶのが一番適していると思います。当機構は特殊法人ですので、「御社」ではありません。私たちも「社員」ではなく、「職員」です。
Q.職場見学はできるの?
できます!ぜひ一度、最寄りの年金事務所をご訪問ください!職場の雰囲気・職員の働く様子を見学することや、実際に現場で働く職員のリアルな話を聞くこともできます。
なお、訪問の際は年金事務所へ事前にお問い合わせの上、お気軽にご来所ください。
採用担当の先輩職員からのアドバイス
Q.社会人1年目に不安だったことは?
初めてのことだらけで不安はありましたが、先輩職員がフォローしてくれました!
私の場合、最初の担当業務で事業主の方の応対をすることが多く、特に緊張しました。それもあり、公私ともにうまくやっていけるか不安でしたが、機構には最初の配属先で、先輩職員が学習指導や各種相談に乗ってサポートしてくれる「チューター制度」があったので、チューターの先輩に相談がしやすく、とても助かりました!
Q.一緒に働きたい人は?
強い責任感と誠実さを持っている方、主体的に行動できる方です!
学業、課外活動、アルバイトなど何でもいいのですが、集団の中で、やるべきことを最後までやり切った経験がある方や、現状をより良くしようと積極的に物事に取り組んだことがある方などは、是非そのお話を聞いてみたいですし、一緒に働いてみたいなと思います。
Q.年金機構あるあるって?
「年金」について、身近な人からも頼りにされることがあるあるだと思います!
公的年金は複雑な点もあり、専門的な知識も求められる制度です。しかしながら、国民のみなさま誰しもが関係を持つ制度ですから、年金の制度や手続きについて、友人や家族からよく頼りにされます。お客様だけでなく身近な人の力にもなれるという、一石二鳥なあるあるです!